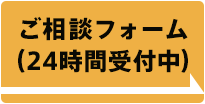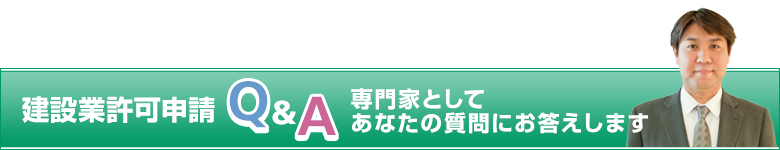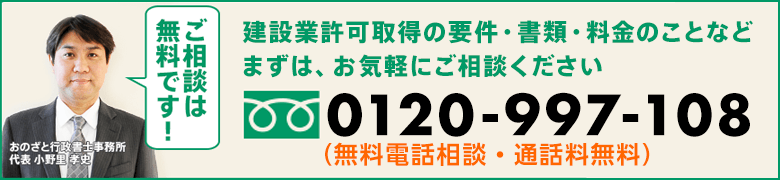私が執筆しています
私が執筆していますおのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するには?
個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可は取得できるのか?
結論から申し上げると、個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得は可能です。
1件の請負金額が500万円(消費税込み)以上の建設工事を請け負うには、法人でも個人事業主でも建設業許可が必要になります。
上記の金額は材料費も含みますので、ちょっとした工事であれば500万円以上になってしまうのではないでしょうか?
この記事を読んで頂いている方のなかには、
「うちは500万以下の工事しか請け負わないから」
という方もいると思いますが、最近は、
「元請会社から許可の取得を求められている」
「同業他社の多くが許可を取得してきた」
「発注者やお客様へのPRにもなる」
などの理由から500万以下の工事しか請け負わない方でも建設業許可を取得するケースが増えてきております。
国土交通省の令和4年度3月末時点での調査結果によると、全国で建設業許可業者数は475,293業者(うち一般建設業が450,901業者、94.8%)で、そのうち個人事業主は70,920業者(14.9%)となっております。
この調査結果からも、個人事業主で建設業許可を取得することは可能なことがわかります。
このページでは、建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するためのメリットやデメリット、経営業務管理責任者や専任技術者になるための条件や必要書類について解説いたします。
- INDEX
- 個人事業主のままで建設業許可を取得するメリット
- 個人事業主のままで建設業許可を取得するデメリット
- 経営業務の管理責任者となるための条件と必要書類
- 専任技術者となるための条件と必要書類
- ワンポイントアドバイス
- 個人事業主で建設業許可を取得されたお客様の声
個人事業主のままで建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事や公共工事が受注できるようになる。
- 売上増加や新規顧客の獲得に繋がる。
- 元請会社や一般顧客(施主)からの信用度が増す。
- 許可を取得していない同業他社への差別化にもなる。
- 許可取得時の申請書類が法人に比べて少ない。
- 法人成りする予定がなければ、申請する際に用意する書類が法人に比べて少ないので比較的短時間での取得が可能になる。
個人事業主のままで建設業許可を取得するデメリット
令和2年10月の建設業法改正までは、
- 法人成り(会社組織に変更する)する際、新たに許可を取得しなければならない。
- 許可取得者(通常は個人事業主本人)が死亡した場合等、許可を引き継ぐことはできない。
という2つのデメリットがありました。
しかし、現在は令和2年10月の建設業法改正により、
- 個人事業主から法人成りする場合であっても建設業許可が承継可能
- 許可取得者である被相続人(通常は個人事業主本人)の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けることで、その相続人が建設業許可を承継することが可能
となっております。
社会保険体制や就業規則等から法人を選ぶ人の方が多い傾向から、法人に比べて優秀な人材(国家資格保有者や実務経験者など)が集めにくいというデメリットはありますが、令和2年10月の建設業法改正前に比べれば、個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得に挑みやすい状況になってきております。
経営業務の管理責任者となるための条件と必要書類
経営業務の管理責任者(略して「経管(ケイカン)」と呼ばれています)とは、営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者(個人事業主や法人の役員など)をいいます。
個人事業主の場合は、本人又は支配人(ほとんど無いケースです)のうち1人が、下記のどちらかに該当しなければなりません。
- ①取得しようとする建設業業種に関する経営経験が5年以上あること。
- 証明するには、5年分の確定申告書の写し(原本提示)と5年分の工事請負契約書、注文書、請求書等が必要です(請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)。
- 個人事業主の経営経験が5年に足りない場合でも、個人事業主以外の経営経験があればそれも使用できます。
具体例- 取得しようとする建設業許可を保有するA社で取締役として3年勤務。
- その後、個人事業主として独立し3期目。
上記の経歴のような場合、A社3年(他社役員経験)+個人事業主2年の合計5年として証明することができます。
証明するには、
- A社の建設業許可通知書コピー等と3年間の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人事業主2年分の確定申告書の写し(原本提示)と2年分の工事請負契約書、注文書、請求書等
が必要です(※請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)。
- ②取得しようとする建設業業種以外の業種に関する経営経験が5年以上あること。
- 証明するには、5年分の確定申告書の写し(原本提示)と5年分の工事請負契約書、注文書、請求書等が必要です(請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)。
- 個人事業主の経営経験が5年に足りない場合でも、個人事業主以外の経営経験があればそれも使用できます。
具体例- 取得しようとする建設業許可以外を保有するB社で取締役として3年勤務。
- その後、個人事業主として独立し3期目。
上記の経歴のような場合、B社3年(他社役員経験)+個人事業主2年の合計5年として証明することができます。
証明するには、
- B社の建設業許可通知書コピー等と3年間の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人事業主2年分の確定申告書の写し(原本提示)と2年分の工事請負契約書、注文書、請求書等
が必要です(※請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)。
多くの方は①の『取得しようとする建設業業種に関する経営経験が5年以上あること』の条件を満たす必要書類を用意して、経営業務の管理責任者になります。
専任技術者となるための条件と必要書類
専任技術者(略して「専技(センギ)」と呼ばれています)とは、営業所に常勤して、その業務に従事する専門的な知識や経験を持つ者をいいます。
建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
※個人事業主ご本人以外の従業員でも要件も満たせば専任技術者にはなれます。
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なりますのでご注意下さい。
(関連:一般建設業と特定建設業の違いについて)
一般建設業の場合
一般建設業の場合は、以下の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
- ①許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者
- 証明するには、卒業証明書+実務経験期間分の工事請負契約書、注文書、請求書等が必要です。(請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)
- ②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格の有無を問わない)
- 証明するには、実務経験期間分の工事請負契約書、注文書、請求書等が必要です。(請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)
- ③許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:二級建築士)を有する者。
- 証明するには、保有国家資格の合格証明書など(原本提示)
特定建設業の場合
特定建設業の場合は、以下の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
- ①許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有する者。
- 証明するには、保有国家資格の合格証明書など(原本提示)
- ②一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 証明するには、実務経験期間分の工事請負契約書が必要です。(原本提示)
- ③国土交通大臣が、①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- これは、以前に実施されていた特別認定講習及び考査に合格した人が該当しますが、現在は実施されておりませんので、上記の①もしくは②で要件を満たす必要があります。
ワンポイントアドバイス
建設業許可を申請するには、上記でご説明した人的要件(経営業務の管理責任者と専任技術者が必要)の他に、
- 財産的要件(一般建設業の場合、自己資本500万円以上あること)
- 営業所要件(独立した営業所であること)
- 欠格要件に該当しないこと
がありますが、一番のポイントは人的要件がクリアーできるかどうかです。
さらに言うと、上記でご説明した証明書類(証明期間分の確定申告書・原本と工事請負契約書、注文書、請求書等(請求書の場合は、入金を証明する通帳なども必要)が用意できるかどうかです。
申請する相手は役所で、書面審査になります。
いくら「俺は高校卒業後、この道一筋20年やってきている」と言っても書面が無ければ認めてくれません。
私は今までに数度、都庁・建設業課の申請窓口で、職員とやりあっている方を見たことがあります。
当事務所にご相談される方でも、証明書類が用意できず(見つからず)に申請を断念される方も多いです。
現在、個人事業主で活動されている方で、すぐに建設業許可を取得する予定がなくても確定申告書・原本や工事請負契約書、注文書などは廃棄せずに保管しておくことをお薦めします。
今すぐに建設業許可を取得したいが、個人事業主として独立して5年経っていない(経営業務の管理責任者の要件を満たせない)方でも、要件も満たせる他の方を経営業務の管理責任者にして許可を取得する事も可能です。
ご不明点やご質問がございましたら、是非お気軽にご相談ください。
個人事業主で建設業許可を取得されたお客様の声
鈴木 様(個人事業主)
神奈川県知事許可・一般建設業・内装仕上げ工事業
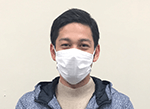
いろいろ事情あって学歴ない方とかもいるし、ずっと仕事してるとかもあるから、今思うと、妻がいなかったら書類もちゃんとそろってなかったかもしれないです。だから「まずとりあえず何でもいいから書類は取っておきましょう」ということですね。勉強云々ではなくて、とりあえず自分がやった仕事の証拠をどこかにまとめておきましょうということを伝えたいですね。
続きはこちら
関 様(個人事業主)
東京都知事許可・一般建設業・管工事業
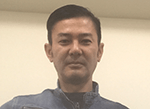
私も請負金額が上がらなかったら考えてなかったんですけど、金額を上げようと思って生きてきたわけじゃないのに、色々なご縁を頂いて、そのご縁に対応するために建設業許可の取得は必要なことでした。もっと早くに許可を持っていれば、そういう人に会うのも早かったかもしれない、と今では考えています。まあ、成り行きで生きてきて、あまり「こういうしよう!」といって目標を決めてそれに向かっていこうと生きてきている人間ではないのですが、いろんな人とご縁があって助けられてここまで来て、そのご縁に応えるには建設業許可が必要だったというところでした。
続きはこちら
牟田 様(個人事業主)
東京都知事許可・一般建設業・防水工事業

他だと「どこでやってもだめだった方、必ず取ります」みたいな感じとか、「何が何でも取ってあげますよ」みたいな感じのことが書いてあるようなホームページとかありましたが、そういうのってどうなのかな?と思って。逆に、どうしても取れない人にしてみればありがたいのかもしれないですけど、僕の場合は全くそういう何が良いのか悪いのかも分からなく今まで普通に自分もやってきたつもりなので、普通のところが良いと思い、小野里さんのところに決めました。
続きはこちら
建設業許可申請の新規取得をお考えの方はこちらもご確認ください。
お役立ちコラム 一覧
- キャッシュレス決済の開始について(東京都)
- 健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について (東京都)
- 建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)
- 建設業許可は継承できるのか?事業承継と建設業許可について
- 建設業許可を自分で申請するには?
- 建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するには?
- 建設業許可(知事許可・一般建設業)を東京で取得するには?
- 解体工事業の登録について
- 経営業務の管理責任者とは?
- 一般建設業と特定建設業の違いは?「一般」と「特定」の違いを解説
- 新型コロナウイルスによる建設業許可等申請手続きの建設業課の対応状況について
- 軽微工事とは?
- 電気工事業者の登録等について
- 経審(経営事項審査)のZ評点の変更について
- 国土交通大臣許可の申請窓口変更について
- 横浜市での建設業許可申請ならお任せください。
- 新外国人労働者受入制度について
- 電気通信工事施工管理技術検定について
- 平成31・32年度(2019・2020年度)東京都建設工事等競争入札参加資格審査(定期受付)について
- 経審(経営事項審査)のW評点について
- 経審(経営事項審査)のZ評点について
- 経審(経営事項審査)のY評点について
- 経審(経営事項審査)のX2評点について
- 経審(経営事項審査)のX1評点について
- 経審(経営事項審査)の審査項目について
- 経審(経営事項審査)の申請手続きについて
- 経審(経営事項審査)の制度について
- 建設産業政策2017+10について
- 外国人技能実習生の労働基準関係法令違反について
- 平成29年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果について
- 建設工事受注動態統計調査報告(平成29年度分)について
- 建設業許可業者数調査の結果
- 建設業働き方改革加速化プログラムとは?
- 登録基幹技能者の主任技術者要件への認定について
- 電気通信工事施工管理技士とは?
- 建設業許可の更新の準備は大丈夫ですか?
- 建築士事務所の登録について
- 経営業務の管理責任者の要件改正のお知らせです。
- 改正建設業法について
- 一括下請負(工事の丸投げ)の禁止
- 建設業法に違反すると?
- 東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請について
- 建設業許可取得会社の役員変更手続きについて
- 太陽光発電設置工事について
- 専任技術者とは?
- 営業所とは?
- 指定建設業とは?
- 欠格要件について
- 許可要件について
- 御社は大丈夫ですか?
- 「大臣許可」と「知事許可」の違いは?
- 建設業許可が必要な場合とは?
- 建設業者とは?
- 建設業界について
当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。